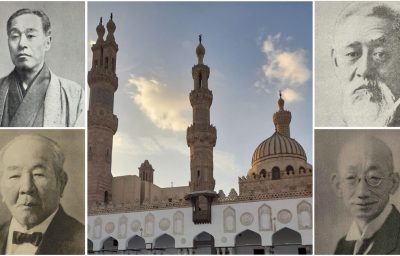COMMUNICATIONS
小さなモノから大きな歴史へ〜昆布が教えてくれる近世日本のグローバリゼーション
江戸時代の昆布の話をしてみようと思います。
丸太町の釜座通に「松前屋」という昆布屋さんがあります。南北朝が終わった明徳2年(1392) 後亀山天皇より屋号を賜り創業した老舗で、現在のご当主で三十二代目。公家や天皇家に昆布製品を献上した所謂「御用」商人で、明治維新の東京奠都の際京都に残り今日に至ります。読者の中には、菓子昆布「比呂女」をご存知の方もおられるかもしれません。明治時代発売で、現在では贈答用に買い求められたり、お汁粉のお口直しとして甘味処で提供されたりしているそうです。
「松前」の屋号で「昆布」を商っている。思い浮かぶのは「松前昆布」。この「松前昆布」、古くから産地ブランド食品として確立されました。中世には狂言のテーマとしても取り上げられます。江戸時代にはその流通は問屋仲間の厳しい管理下に置かれ、下関経由の西廻り航路で大坂に輸送され、そこから京・江戸などの消費地に送られていました。一方海の向こう、昆布が育たない清朝では、当時甲状腺障害が流行していて、その予防効果があるとされるヨードを含む昆布の需要が伸び、長崎からの主要輸出品になりました。
この昆布の国際化に、重要な役割を担ったのが富山の薬売だったというのは余り知られていません。寛永16年 (1639) 加賀藩の支藩として立藩された富山ですが、当初から財政難続きで、その打開策が薬売でした。このため全国を22組に分け、各々を売薬人グループに担当させました。そのひとつが、こちらも財政難に苦しむ薩摩藩でした。当時の薩摩は昆布を琉球王国を通して需要の高い清朝に輸出していましたが、19世紀に入り松前昆布の調達と引き換えに、富山の売薬を認可しました。一方富山売薬人にとっても薩摩藩は格好のマーケットだったようで、一時期富山薬商が所有する船で松前で密買いされたものが薩摩にもたらされ、中国に向けて密輸されていました。
Food and foodways (単に「食文化」ではなく「食」を通して政治・経済・文化・社会等人々の生活のあらゆる側面を見るアプローチ)を歴史学の観点から勉強し、「食」に関わった「人」、特に市場に関連する各地の商人や生産者、に関心を向けてきました。
「松前昆布」は、こんな Food and Foodways の多くの側面を語ってくれます。当時の最北端と最南端の人々が、その中間地点の人々を介して結ばれたり、その昆布が「薬」として密売され鹿児島・琉球・清朝の人を繋げたりと。「食」はそれ以上のことを教えてくれます。

平瀬徹斎著・長谷川光信画『日本山海名物図会』(1754年)
民家の屋根で干す巨大昆布を描き、松前の名物と紹介されています。(国際日本文化センター図書館蔵)

現在の松前屋。暖簾に「御用所」の文字が見える。昆布屋の暖簾ときいて山崎豊子のデビュー作「暖簾」を思い浮かべる方もいるかと思います。(写真筆者)

明和7年、二十三代目当主がその功績を認められ後桜町天皇から下賜された鋏箱。(写真筆者)